音響コミュニケーション研究室
- 音響工学
- VR/AR/MR

快適な生活と豊かな文化を支える音技術の研究
コミュニケーションは人間の最も重要な行為の一つです。コミュニケーションは媒介となるメディアによって様々な特色を持ちます。本研究室ではメディアの中でも「音波」に着目し,音コミュニケーションをより豊かにする技術に関する研究を行っています。
音響コミュニケーション研究室教員紹介

池田 雄介教授
Yusuke IKEDA
2007年 早稲田大学大学院 博士取得(国際情報通信学)同年 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 研究員. 2009年 独立行政法人 情報通信研究機構 研究員. 2011年 京都大学大学院 工学研究科 研究員. 2013年 東京電機大学 環境情報学部 環境情報学科 プロジェクト助教. 2015年 早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 助教 / 東京電機大学 情報環境学部 研究員. 2017年 東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科助教
2021年より同准教授となり,現在に至る. 空間音響や音場の可視化など、音響測定および音響情報処理の研究に従事
研究事例

多チャンネルスピーカを用いた三次元音場制御
音を使って,あたかも人が存在するかのようなVR空間を作り出す研究を行っています。物理的に正確な音場の制御を行うための信号処理,計測技術など基礎的な研究から,実際に体験出来るシステムの構築まで幅広く研究を行っています。写真は,制御する音場を空間的に限定することで再現精度を高める技術に,頭部の位置をトラッキングする技術を組み合わせて,聴取者の周辺のみを正確に制御する動的局所音場合成システムです。人間本来の音空間知覚に合わせた究極のVR体験を目指します。
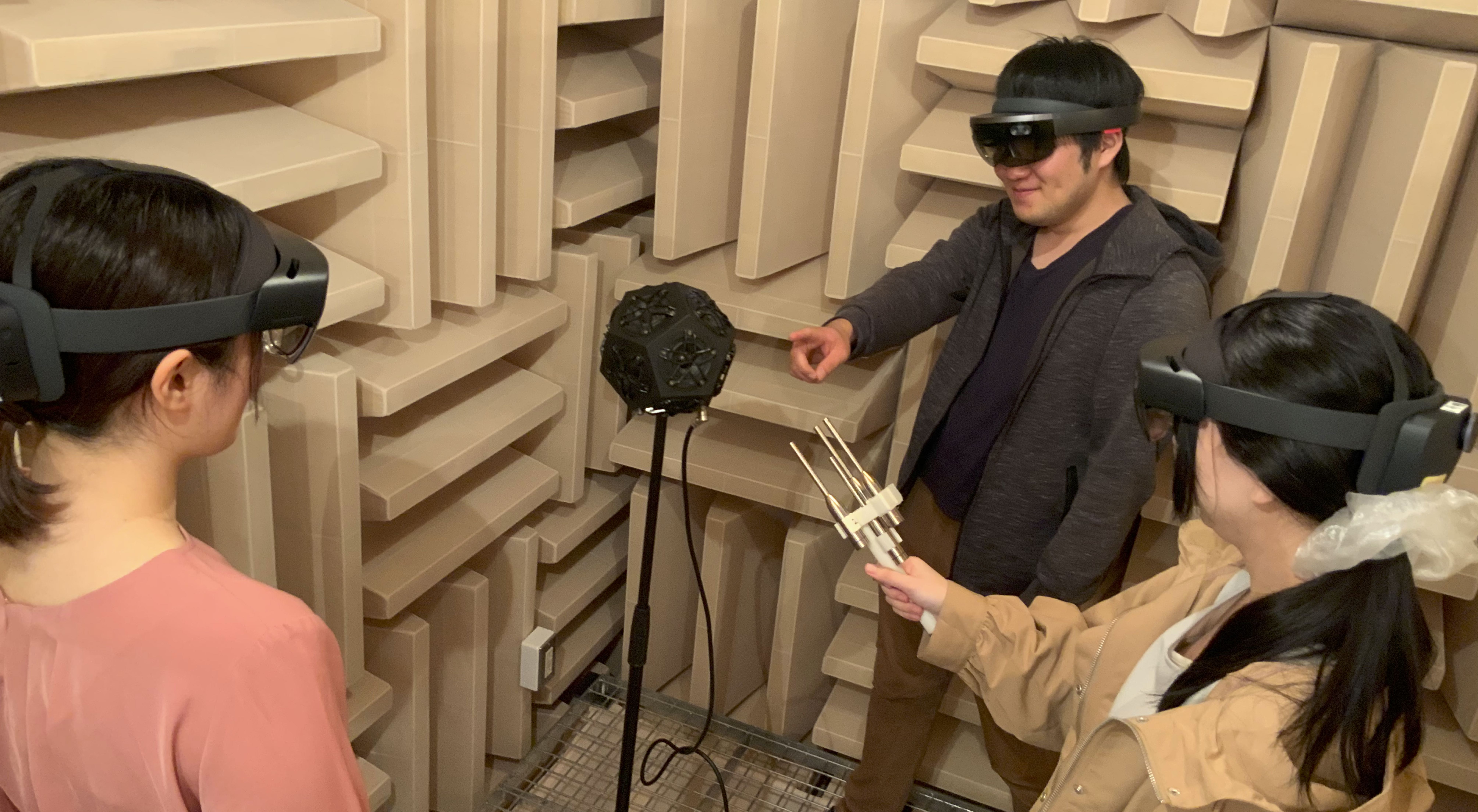
複合現実技術を用いた音空間の可視化
音がどこからどのように伝搬しているかを聴覚だけで把握することは容易ではありません。ホールや部屋の響きや遮音性能の改善,あるいは異音する製品の改良など,音の問題解決には,音の伝搬を知ることが重要です。我々は,複合現実技術を用いて,手持ちのマイクロホンで空間内を走査することによって,リアルタイムに音場が可視化されるシステムの研究開発を行っています。従来手法と比べて,手軽に大量のデータを計測でき,即時,その部屋自体に可視化されるため,問題の原因となった物と音の伝搬を関連付けて観察することができます。
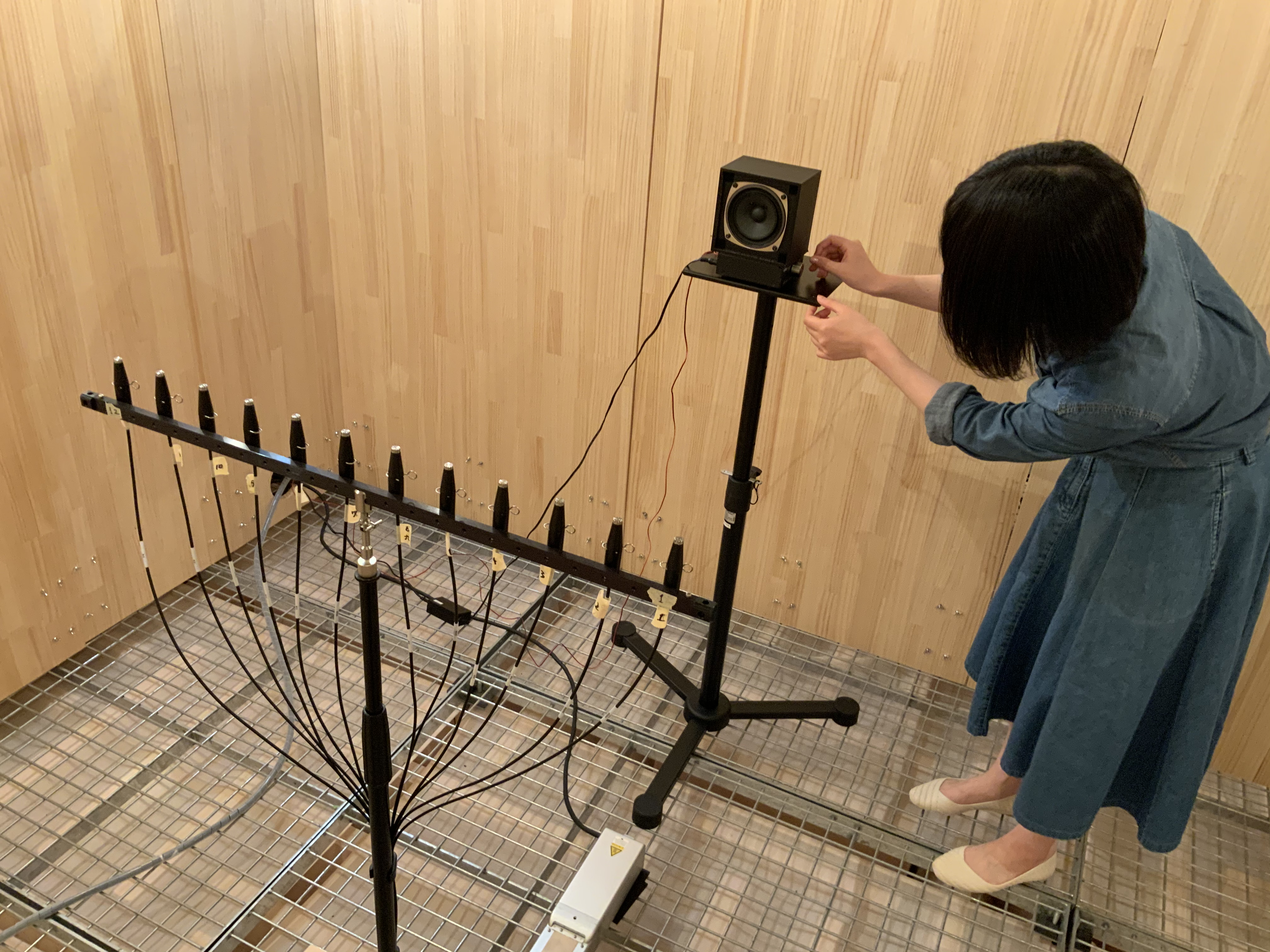
音場の計測と分析
音は計測する位置によって変化するため,音空間の計測には多数の点でマイクロホンを使った計測が必要となり,これは必ずしも容易ではありません。音場の可視化の研究では,リアルタイムにおおよその音空間を理解することを目的としていますが,目的によっては,音場情報をより正確に知る必要があります。そこで,我々は,少数のマイクロホンで計測したデータから,音の物理モデルに基づいて,音空間をモデル化する研究を行っています。モデル化された音空間を音空間情報の補間や分析に利用します。
研究室の生活
研究室配属後,まず,相談をしながら研究テーマの方向性をできるだけ早く決定します。近い研究テーマの学生同士でチームを組みつつ,先輩や先生に教わりながら,研究に必要となる道具の使い方,専門用語の理解,数学,プログラミング技術を伸ばします。同時に,関連研究となる英語論文を読み,研究の構造の理解と読解力,英語力を鍛えます。また,早い段階で学外発表の目標を立て,研究のスケジュールを作成します。目標に向かって作成したスケジュールを常に見直しながら,研究を進めることで,自ら時間を管理する能力を身につけます。毎週のゼミでは,研究の進捗発表をしながら,ディスカッションをすることで,研究を進めつつ,各自の質問力を鍛えます。また,スライドの作り方や発表方法をお互いにチェックしあうことで,プレゼンテーション力を伸ばします。特に大学院進学を目指す学生は,学部4年時から学外発表を目指して研究を進めますので,毎日,活発に活動します。また大学院では,国際会議での発表を必ず行い,最終的には学会誌への英語論文の投稿を目指します。研究活動には多くの失敗もありますが,困難な課題に取り組む仲間と共に切磋琢磨し,小さな成長を継続することで,大きな成長に繋がります。
先輩の声
情報メディア学科には珍しく、研究に物理や数学が必要になります。私も最初は苦戦しましたが、研究室内で勉強会が開かれており、関連する知識を学ぶことができました。また、人によってはかなりの頻度で学会発表もあります。私自身、必要な知識を身に着けたり、学会発表に参加したり、研究室に配属されてから様々なことに取り組んできましたが、どれも先生や先輩方の手厚いサポートのおかげでできたと思っています。自分に自信のない人にこそ、手厚いサポートが受けられるこの研究室をおすすめします。(修士課程 H.M.)
学会への参加に積極的な研究室という印象です。自分はこれまで毎年複数回学会発表を行なってきました。研究室配属前は人前で話すことがとても苦手でしたが、学会での発表機会を通して少しずつ人前でも話せるようになっており、成長していることを実感しています。また、学会発表という目標(締め切り?)が定期的にあるからこそ、だれずに研究活動に打ち込むことができ、充実した大学生活を送れていると感じています。せっかく大学に入ったのだからがっつり研究したい!という人には向いている研究室ではないでしょうか。(修士課程 Y.W.)
とりわけ音がやりたいという気持ちはなかったのですが,信号処理に興味をもってこの研究室に入りました。最初のころは,まともにプログラムも書けず,先生に手取り足取り教えてもらいながら,日々研究に取り組んでいました。今では,先生とも色んな議論ができるようになってきて,少しずつ自分の成長を感じるようになりましたが,それもすべて,池田先生の手厚い指導と研究室メンバーによるサポートのおかげです。研究は決してラクではないので,心が折れそうになるときはたくさんありますが,研究室のメンバーは皆とても真面目でしっかりしているので,後輩も含めて彼らの姿を見て自分も励まされています。とはいえ,みんなで雑談したり,合宿で山登りをしたりなど,研究以外の楽しいこともあるので,苦しくも楽しい充実した研究生活を送れます。音に興味がある方はもちろん,漠然とでも"成長したい"と思っている方には,ぴったりの研究室だと思います。(博士課程学生)
大学に入学したときから何となく音関係の研究がしたいと思い,この研究室を希望しました。この研究室では週一回のゼミの他に,先生との研究の打ち合わせや基礎知識を身に付けるための勉強会が週一回ほど行われるため,研究室内での交流が多いです。私自身,一人で黙々と勉強や研究を進めることが苦手なので,先生や先輩後輩たちと協力し合いながら研究を進められるこの研究室は私には合っていると思っています。また,どんなに些細な質問でも先生や先輩方が丁寧に答えてくれるので,今後上手く研究を進められるか不安な人にとってはおすすめの研究室ではないかと思います。(修士課程 Y.O.)